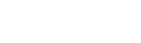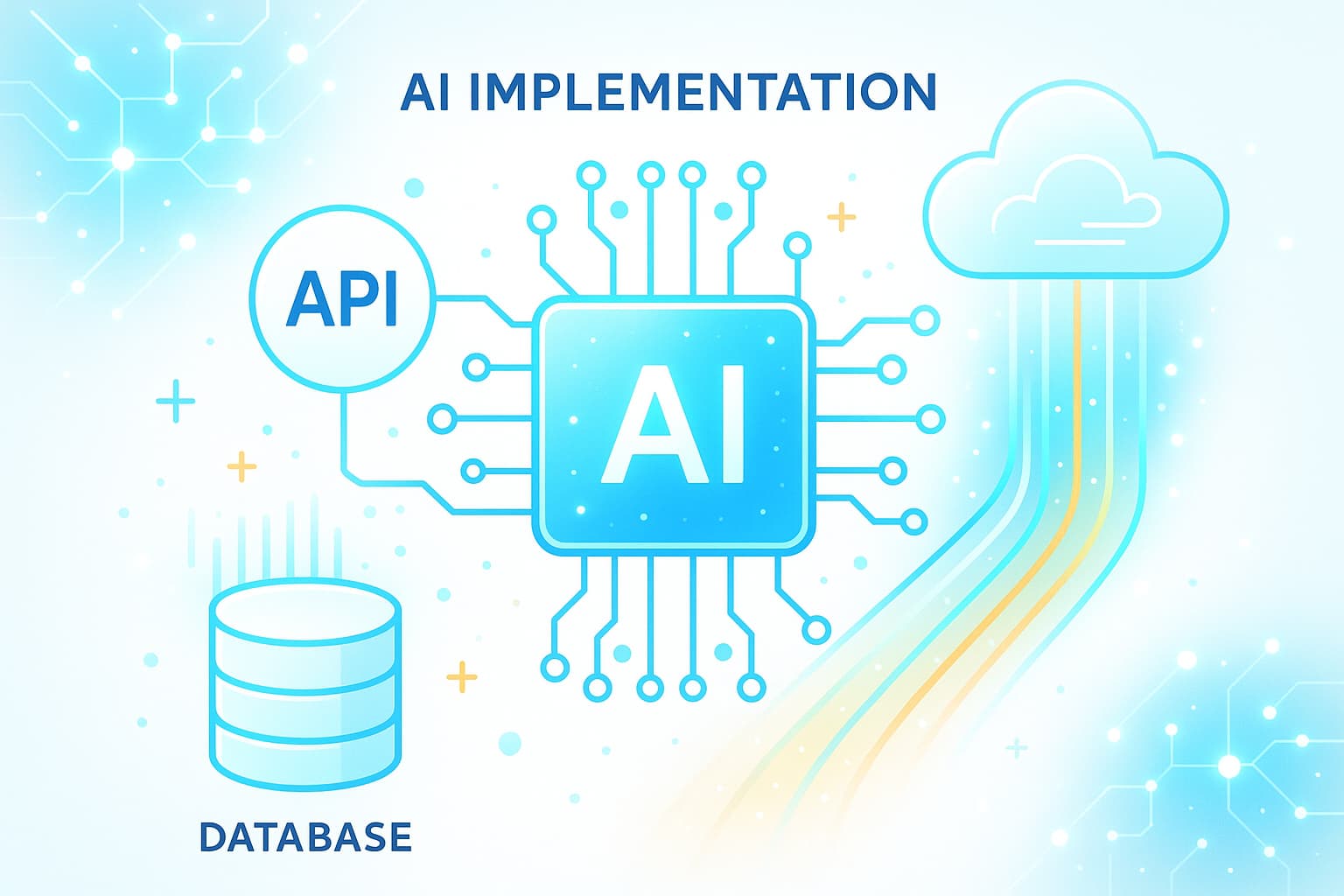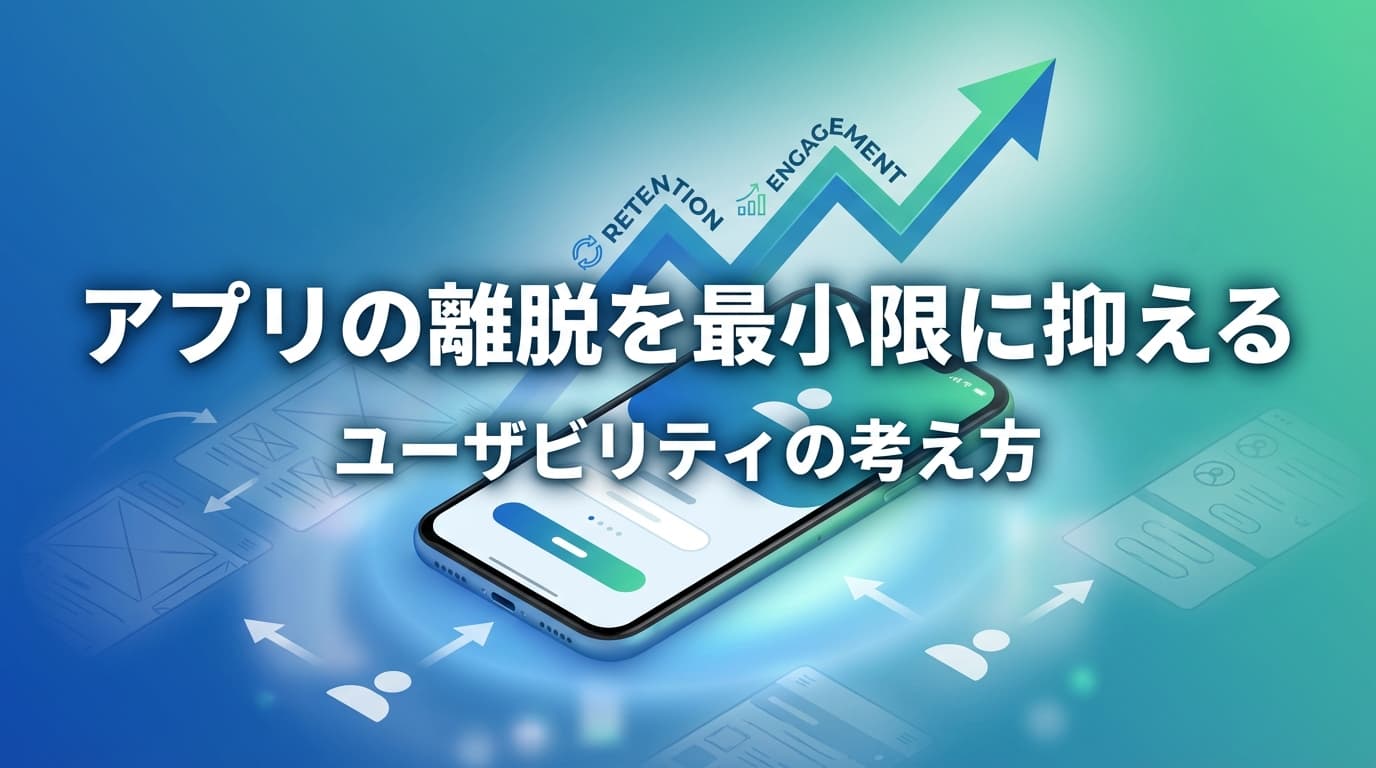iPhoneアプリ開発の外注の費用相場と内訳│Androidとの比較や補助金情報
スマートフォン市場では、iPhoneアプリ開発の需要が依然として高く、多くの企業が自社アプリを開発し、顧客体験の向上や業務効率化を図っています。
しかし、開発費用がどの程度かかるのか、Androidアプリ開発との違いや補助金制度の活用方法について知ることは、アプリ開発を成功させるために重要です。
本記事では、iPhoneアプリ開発の費用相場とその内訳、Androidとの費用比較、さらには補助金情報について詳しく解説します。