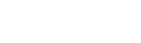LLMO対策のやり方はSEO対策から大きく変わらない|AIの回答に自社情報を反映させるための基礎知識
近年、情報を探す手段はGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGeminiなどの生成AIへと広がっています。これに伴い、Webサイト・サービス運営者が意識すべき新しい考え方が「LLMO(大規模言語モデル最適化)」です。 「難しそう」と感じるかもしれませんが、その本質はこれまでのSEOと地続きにあります。本記事では、Webサイトやサービスの情報をAIに正しく届けるための「LLMO対策のやり方」を、具体的かつ実務的な視点で解説します。