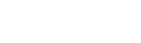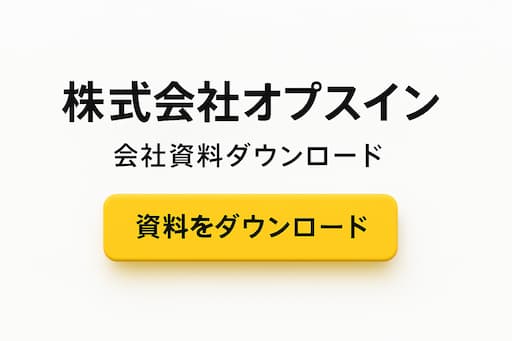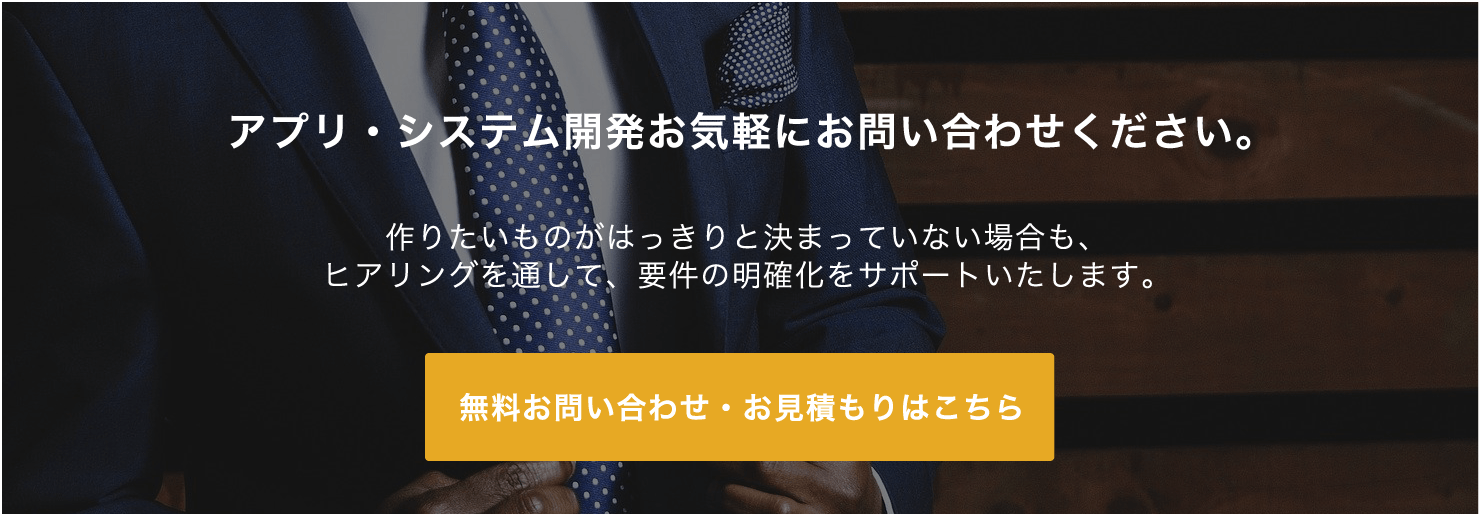新規事業はスピードが命。ただ、セキュリティが弱いとストアの審査や外部の確認(ストア/顧客/パートナー)で止まり、事故なら販売停止や信頼低下につながります。本記事は、今日から決められる5つの方針と、3ステップで進める方法を解説します。B2B/B2Cどちらでも使える基本形です。
1. セキュリティは事業の必須条件
アプリは「動くかどうか」だけでは評価されません。「安心して使い続けられるか」が問われます。B2Cではストア審査やプライバシー表示の不備が差し戻しや低評価につながり、B2Bでは顧客やパートナーからの質問票や第三者チェックに答えられないと機会損失になります。万一の事故は販売停止・返金対応・ニュース化による信頼低下へ直結します。スピードと安全は両立できます。何を集めるか、誰が見られるか、どう点検するかを最初に決め、日々の運用に組み込むことが近道です。
昨今特に多い、クレジットカード情報漏洩問題への充分な対策も必要です。
2. まず決めるべき5つの方針
まずは”何をどう守るか”の方針を決めていきましょう。実際の設定や運用は次の3章(実行編)で扱います。
・集めるデータ/集めないデータ(個人情報は最小限)
目的に不要なデータは集めない、と決めます。例:生年月日や正確な位置情報は
本当に必要な時だけにします。クレジットカード情報は自社で扱わない方針で、
決済代行やApple Pay/Google Payを使います。
・見られる人・触れる人の範囲(社内・委託先の権限)
管理者/運用/閲覧など役割を分け、最小限の権限に。
本番に変更を反映できる人は限定し、重要変更は二重承認にします。退職・契約終了時は「即停止」までをルール化。
・外部の機能やサービス(解析・通知・決済など)の一覧と目的
使う理由と送るデータを一覧化。「どこへ」「何を」出すか、説明できる状態に。
タグマネージャや外部スクリプト/CDNも一覧に含めます。決済は“カードに触れない方式”(ホステッド決済/公式SDK)を前提にすると決めます。
・トラブル時の連絡先と役割(誰が判断し、誰が動くか)
初動フローを1枚に。判断者、技術対応、広報/営業の連携先まで明確化。決済代行会社の緊急連絡先も入れておくと安心です。
・点検の頻度と方法
リリース前チェック、月1の更新、年1回の第三者診断など、頻度と範囲を決めます。
改ざん検知(無許可の変更を自動通知)と侵入検知(不正ログインや異常アクセスの通知)を導入する方針をここで決め、外部スクリプトはSRI/CSPで正しい版・想定外通信を管理する方針も決めます。
重大な問題は7日以内に直す、といったSLA(期限)もここで決めます。
3. 最低限、実行すべき5つ
2章の方針を元に、具体的な実行に落とし込んでいきます。ここでは最低限必要な実行を5つお伝えします。
・ログインを強くする(多要素認証=パスワード以外も求める)
管理画面や社内ツールも含めて多要素認証を有効化。SSO利用時もMFA必須に。
必要ならIP/デバイス制限も併用。バックアップコードの保管も決めます。
・権限を最小限にする(不要な閲覧・操作を許さない)
権限によって閲覧・編集の範囲を設定します。役割(管理者/運用/閲覧など)を作り、デフォルトは「見えない・触れない」ように
します。タグ/スクリプト変更は申請制+二重承認。月次のアクセス見直しと、退職・契約終了時の即停止を徹底します。
・大事な情報は暗号化し、秘密はアプリ内に置かない
保存・通信は暗号化が前提です。鍵やトークンは専用の保管庫を使い、アプリ内に埋め込まないようにします。
繰り返しになりますが、カード情報には“触れません”。ホステッド決済/公式SDKで実装し、ログや問い合わせにカード番号・CVCが残らないようマスキング設定を入れ、テストカードで確認します。
・使っている部品や外部機能を毎月更新する(放置しない)
月1の更新日と担当者を固定。バージョン一覧を作り、古いSDKやライブラリは計画的に更新。不要になった外部機能は削除します。
・記録と通知を有効にする(監査ログ=重要操作の履歴+異常アラート)
ログイン失敗の連続、権限変更、データ大量出力などにアラートを設定。
改ざん検知を入れる(重要ファイルや決済ページ、主要スクリプトの“無許可の変更”を自動で通知=ファイル変更監視/FIM)。
侵入検知を有効化(不正ログイン、ログイン失敗の急増、異常アクセス等のアラート)。
外部スクリプトの正当性チェック:SRI(正しい版の印)とCSP(想定外の読み込み/通信のブロック・通報)を設定。
週次でダイジェストを確認し、月次で運用を見直します。
4. セキュリティ対策3つのステップ
これまでご紹介したまとめになります。この3ステップは「決める→始める→確かめる」の順に進みます。最初に方針と体制を固め(ステップ1)、次に実装と運用のルーチンを動かし(ステップ2)、最後に外部の目で確認して公開情報を整えます(ステップ3)。目安は最初の3ヶ月ですが、状況に応じて短縮・延長して構いません。
ステップ1(方針を固める)
– データの棚卸し(集める/集めないの表を作る)
– 外部機能・サービスの一覧化(目的と送信データを記録。タグマネ/外部スクリプトも含む)
– ログイン強化の方針を決める(多要素認証を有効化)
– 決済方式を決める(カード情報は扱わず、代行会社/Apple Pay/Google Payを採用)
– 改ざん検知/侵入検知の導入方針を決める(どこを監視し、誰が受け取るか)
– 外部スクリプトの管理方針(SRI/CSPを採用し、想定外の読み込みを止める/通報する)
– 代行会社の要件を確認(PCI DSSという国際基準に準拠、連絡体制)
– 連絡体制と初動フローを1枚にまとめる(改ざんが発見された時の手順、代行会社の緊急連絡先も記載)
– 到達点:方針1枚/一覧1枚/初動フロー1枚が揃う
ステップ2(実装と運用を始める)
– 権限の整理(見える人を絞る、役割を分ける。タグ/スクリプトの変更は申請制+二重承認)
– 月1の更新ルールを開始(担当と日付を固定)
– 記録と通知を有効化(監査ログと基本アラート)
– 改ざん検知を設定(重要ファイル/決済ページ/主要スクリプトの変更を自動通知)
– 侵入検知を設定(不正ログイン、異常アクセス、エラー急増を検知)
– 外部スクリプトの正当性チェックを設定(SRIを付与、CSPで想定外の読み込み/送信をブロック・通報)
– 決済はホステッド決済/公式SDKで実装し、カード番号が自社に来ないことを確認
– ログ/解析/問い合わせにカード番号・CVCを残さない設定(パターンマスキング)
– 社内オペのルール化(電話やチャットでカード番号を受け取らない)
– 外部の確認に備え、想定質問の回答下書きを用意
– 到達点:権限整理完了/更新運用開始/記録とアラート有効/改ざん・侵入検知が稼働/SRI/CSPが有効/決済の“非接触”実装完了
ステップ3(外部チェックと公開情報を整える)
– 第三者の簡易診断を実施(決済ページや重要スクリプトの改ざん耐性も確認)
– 見つかった問題に期限を付けて修正(重大は最優先)
– 改ざん/侵入検知のテスト(疑似変更・疑似不正ログインで通知が来るか確認)
– 決済周りの最終確認(テストカードで動作、ログに残っていないか)
– 代行会社のPCI DSS証明の有効性を確認(年1回の予定も設定)
– 方針と運用を会社資料(セキュリティの基本方針)にまとめる
– 到達点:重大な問題ゼロ/サービス資料完成/改ざん・侵入検知が運用に乗り、年次確認の予定が入っている
5. よくあるつまずきと回避策
外部の機能(SDKなど)が不要なデータを送っていてストアから差し戻される、という相談はよくあります。使う目的と送るデータを一覧にし、不要な送信はオフにするだけで多くは防げます。ログに個人情報を書かないルールも合わせて定めましょう。
決済でのつまずきは「自社フォームでカード番号を直接入力させている」ケースです。方針はシンプルに、“カードには触れない”。代行会社のホステッド決済や公式SDKに切り替え、ログや問い合わせツールにもカード番号・CVCが残らない設定(自動マスキング)を入れてください。
外部の確認や問い合わせへの回答が遅い、担当者によって内容がバラつく、という問題も頻出です。「基本方針・データの置き場所・点検頻度」をサービス資料にまとめ、定型の回答を用意しておくと、スピードと一貫性が上がります。最後に、退職者や委託先のアカウント停止忘れは重大事故の原因になり得ます。月次のアクセス見直しと「やめたら即停止」の運用で予防を徹底してください。
6. 進捗の目安(数値)
– セキュリティが原因のトラブルは起こさない(ゼロを維持)
未遂やアラートは別で記録し、ゼロ継続月数を管理すると実態が見えます。
– 重大な問題は7日以内に修正
期限(SLA)を決め、例外は責任者承認に。修正完了までの見える化が重要です。
– 外部機能・部品の更新遅れは30日以内に解消
月1の更新日と担当を固定し、遅延があれば次回スプリントで必ず解消します。
– 外部の審査・確認にかかる期間は前回より20%短縮
会社資料と回答テンプレを整えるだけで短縮効果が出ます。期間を計測し、改善を続けます。
– カード情報の自社取り扱いはゼロ(すべて代行経由)
自社サーバ、ログ、解析、問い合わせツールのいずれにも残らないことを点検します。
– 決済代行のPCI DSS証明を年1回確認
証憑(有効期限やURL/証明書)をサービス資料に保存し、更新時期をカレンダー化します。
まとめ
セキュリティは「出すための壁」ではなく「事業を止めないための土台」です。先回りして方針と運用を土台化すると、ストア審査や顧客からの確認に即答でき、直前の手戻しや販売停止を避けられます。
最初に方針を5つ決め、対応する実行を回し、3ステップで「決める→始める→確かめる」を繰り返せば、スピードと安全は両立できます。特に決済は“カードに触れない設計”が重要です。目標はゼロ事故。月次の更新と記録・通知の運用で、日々の小さな改善を積み上げていきましょう。
支援のご案内(お問い合わせください)
弊社は、セキュリティ要件が厳しい大手企業さまや証券会社さま案件の実績があり、設計から運用まで幅広い知見があります。新規事業フェーズでも現実的に回る「過不足ない対策」をご提案します。
まずはお問い合わせください。状況をうかがい、最短で効果が出る進め方をご一緒に設計します。
Author Profile
-
東京都のwebアプリ、スマートフォンアプリ開発会社、オプスインのメディア編集部です。
・これまで大手企業様からスタートアップ企業様の新規事業開発に従事
・経験豊富な優秀なエンジニアが多く在籍
・強みはサービス開発(初期開発からリリース、グロースフェーズを経て、バイアウトするところまで支援実績有り)
これまでの開発の知見を元に、多くのサービスが成功するように、記事を発信して参ります。